禅はインド→中国→⽇本と伝わってきたものです。
鈴木大拙(日本の仏教学者・文学博士)は、禅についての著作を英語で執筆し、日本の禅文化を海外に広く紹介しました。
その後、アメリカではスティーブ・ジョブズが坐禅を日常的に実践していたことでも知られ、禅は多くの起業家に取り入れられるようになりました。
そしてそのブームは、再び日本へと逆輸入される形で戻ってきました。
禅とは?
禅の教えそのものが「不⽴⽂字(ふりゅうもんじ)」です。
⽂字や⾔葉で⾔い表せない、実践や体験で体得するものです。
頭でっかちになることを戒める、体験重視を教えとします。
禅は仏教から発⽣した実践哲学のようなものであって、真実を悟ることと等しい価値観で、真実を体現することを主題としています。
仏になることを⽬指すというよりも、すでに仏であることを⾃覚した上で、仏として⽣きることを⽬指しています。
禅宗とは、「教祖と聖典のない宗教」です。
教祖も聖典もないので、これが禅だと定義するのは難しいです。
なぜ、禅を学ぶか
禅=⾃由への道
禅とは⾃⼰の存在の本性を⾒抜く術であって、それは束縛からの⾃由への道を指し⽰す。
⾔い換えれば、我々⼀⼈⼀⼈に本来備わっているすべての⼒を解き放つのだ、ということもできる。 (鈴⽊⼤拙の言葉)

どうやって禅を学ぶか?
聖典がないので、禅を学ぶ方法としては、下記が挙げられます。
- 坐禅をする(調⾝、調息、調⼼)まっすぐ座り、ゆっくり呼吸する
- ⾃分の頭で考える(演繹法)
- 禅僧の⾔葉やエピソードを聞く、読む
- 禅語から学ぶ(禅語とは禅の教えを伝えていく中でできた短い⾔葉)
- 実践する・体験する・体を動かす(考えるより動く)
坐禅
道元(曹洞宗)の坐禅は、「只管打坐(しかんたざ)」、「ただ ひたすらに坐る」という意味です。
坐禅は何かを求めて⾏うもではなく、坐禅をしている状態そのものが悟りの体現なのだから、何も求めずただひたすらに坐禅に打ち込む。
その真意は、坐禅に⽬的はない、ということです。
⼼を安らかにするために坐禅をする、悟りのために坐禅をするなど、私たちは「〇〇のために」という⽬的⾄上主義に陥っています。
- そうではなく、とにかく坐る。ただ坐る。⼼地良く坐る。
- 成果や⾒返りを期待せず、今に張り付く
禅語
禅語とは、禅の教えを表した言葉です。
禅の世界では、こうした言葉を通じて禅の真意を捉えることがよくあります。
数ある禅語の中から、いくつか印象的な言葉を以下にご紹介します。
⽇⽇是好⽇(にちにちこれこうじつ)
毎⽇を過ごしていれば、当然いいことも悪いこともある。
しかし、⾃分がいる環境に逆らわずに、
その中でできることに真っ直ぐに対峙していけば、
どんな⽇でも新鮮でいい⽇だということ。
⾯壁九年(めんぺきくねん)
達磨⼤師が少林寺の壁に向かって9年の間、坐禅を組んでついに悟りを開いたと
いう故事から、転じて、⽬的のために⾟抱強く粘り抜くことをたとえていう ⻑い年⽉、ひとつのことにただひたすら向き合う
本来無⼀物(ほんらいむいちもつ)
⽣まれた時は何も持っていない
死ぬ時も何も持って⾏けない
⼈間は本来、何も持っていない
欲望や、物への執着を捨てる
禅と目的の関係性
禅においては、「目的を手放すこと」が大切にされています。
これは、現代で重視されている論理的思考や目標志向とは、一見すると矛盾しているように見えるかもしれません。
しかし、以下の観点から見ると、禅と目標の関係性には深いつながりがあることが分かります。
禅は「目標の質」を高める
禅は「より静かに、しなやかに、力強く目標に向かうための“心の使い方”」
禅の実践は、焦りや過剰なコントロールを手放し、本質に集中する力を育ててくれます。
「今ここ」と「未来」のバランス
- 禅:「今ここ(現在)」に集中し、瞬間を大切にする。
- 目標:「未来」のあるべき姿を描き、そこに向かって進む。
➡ 禅は「今に在ること」、目標は「未来に向かうこと」。
矛盾するように見えて、“今を丁寧に生きること”が目標の最短ルートになるという点で重なります。
「執着」と「意図」の違い
- 禅: 結果に執着せず、プロセスそのものに没頭することを尊ぶ。
- 目標: 結果(目的)に向かって努力することが前提。
➡ 禅的なあり方は、「目標を持ちつつ、それにとらわれない意図の持ち方」を教えてくれます。
“結果は流れに委ね、行為には全力を尽くす”という姿勢。
「無為」と「意志」の融合
- 禅: 無為自然。不要な力みを手放し、流れに身を任せる。
- 目標: 意志と努力によって状況を変えていく。
➡ 禅的実践は「やるべきことをやる」中で、力まない行動を可能にします。
むしろ、目標達成のために“無駄な力を抜く”技術として禅は機能します。
「目的のない行為」の力
- 禅では、座禅や作務(掃除など)を目的なく行います。
- この「目的にとらわれない行為」は、集中力・継続力・心の静けさを育てる。
➡ 結果ばかりを追うと続かない。
禅は「行為そのものを喜びとする力」を養い、目標を長期で支える土台になります。
「自己実現」と「自己超越」
- 目標は多くの場合、自己実現(○○になりたい)に基づいています。
- 禅はその先の、自己を超える(無我)感覚に導きます。
➡ 禅的視点は、目標を手段と見なし、“目標の向こう側”にある成長や在り方に気づかせてくれる。
最後の問い
自分に使える禅的問い
- あなたが本当に大切にしたいことは何か?
- この目標の裏にある「思い」は何か?
- 今日1日、何を丁寧にできるか?

禅に関する書籍
- 禅とオートバイ修理技術: 価値の探究 (シリーズ精神とランドスケープ) Robert M. Pirsig (著), 五十嵐 美克 (翻訳)
- 禅マインド ビギナーズ・マインド 鈴木 俊隆 (著), 藤田 一照 (翻訳)
※「戦略スクール」の講義から一部抜粋
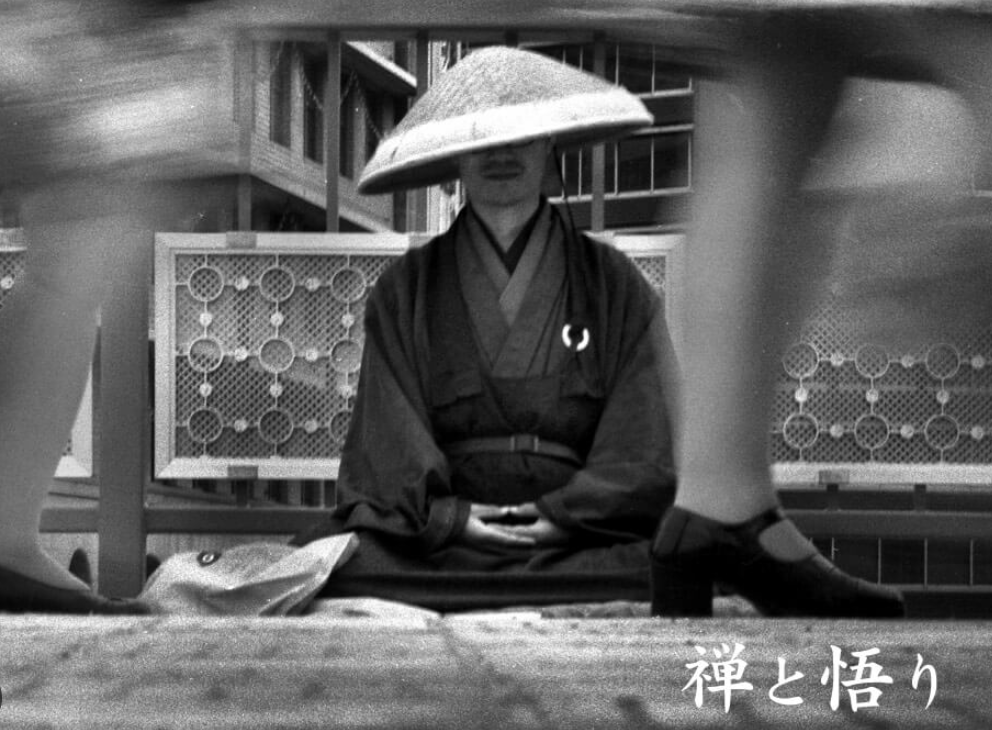
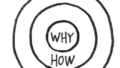

コメント